僕が東温アートヴィレッジ構想のために、地域おこし協力隊に入った今年の1月に、東温市を「舞台芸術の聖地」にしたいと言われ、そのモデルとして、早稲田小劇場が40年以上前に移転した利賀村の名前を挙げられた。
確かに利賀村は「演劇の聖地」として現在までその名を馳せているが、実は僕が2年間早稲田小劇場に身を置いていたのは、まさに移転する前後であった。早稲田大学の近くにあった「モンシェリ」と言う名の喫茶店の2階に居を構えていた早稲田小劇場が、期限が切れたのを機会に別の場所に移転しようとして、富山県の辺鄙な山奥にある利賀村の合掌造りの民家を借り受け、そこを演劇の拠点にしようとしたわけである。
なぜ、都会から離れたのか、なぜ冬になるとすっぽり雪に埋もれてしまうような豪雪地帯に移転しようとしたのか、その頃の僕には不明だったが、演出家の鈴木忠史氏の書かれた本を読むとおぼろげながら分かって来る。もっとも、どうも利賀村に決まったのは偶然のようで、理由は後付けの感が拭いきれないが。
とは言っても、「早稲小」の芝居の質にぴったりだったことは疑いようがない。あたかも空間に浮かんでいるかのような舞台。しかも、築何百年か分からないが、その民家に住んでいた人たちの怨念のようなものまで感じられるから不思議だ。これは東京の劇場をいくら探しても手に入らない空間だ。
勿論お金があって、好きなように劇場を作れるような条件の劇団なら……いや、その場合には現代的な舞台づくりがなされ、肉体とはかけ離れた電気仕掛けの劇場が立つことになるだろう。そう、お金がないというのも利賀村を選んだ理由らしい。あくまで偶然の産物だ。(ただし、僕自身、全国の市町村から東温市を選んだのも、勿論きっかけはあるけれど、決めてから、ああだこうだと理由付けをしているので偉そうなことは言えない。)
地元の村人の胡散臭いものを見るような目に迎えられた東京の小汚いアングラ劇団が、やがて村人たちの関心を招き、再びやって来た5年後の期限切れの際には、向こうから残って欲しいと切望されたのだ。
その後、世界中の演劇人から「利賀詣で」とまで言われる利賀演劇フェスティバルとして生まれ変わったことはご存知の方も多いだろう。残念ながら移転1年で辞めてしまった僕のあずかり知らぬところではあるが、それは忠さん(ちゅうさん。劇団員は親しみを込めて鈴木氏をこう呼ぶ)の書いたいろいろな本で読んでいただくとして、僕の感じた利賀村での最初の一年を思い出しながら伝えたいと思う。
(つづく)
Jin Tadano
最新記事 by Jin Tadano (全て見る)
- 若き巨匠【コラム⑮】 - 2020-09-25
- 新しいチャレンジ!(2/2)【コラム⑭】 - 2019-09-13
- 新しいチャレンジ!(1/2)【コラム⑭】 - 2019-09-12









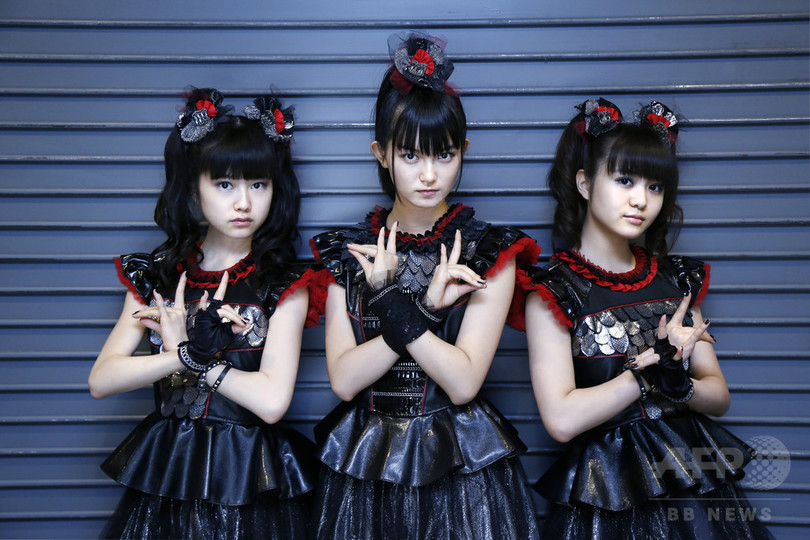
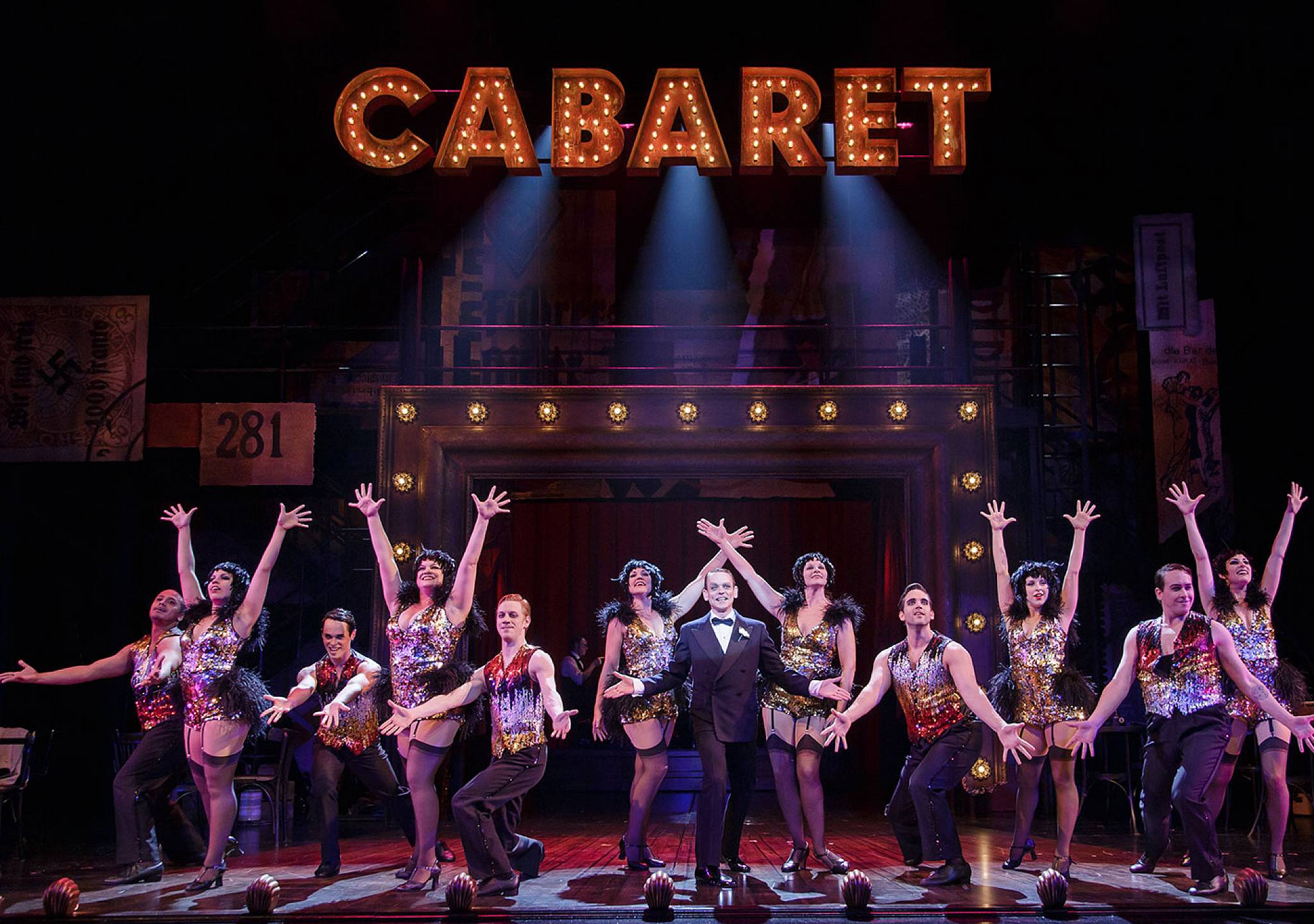



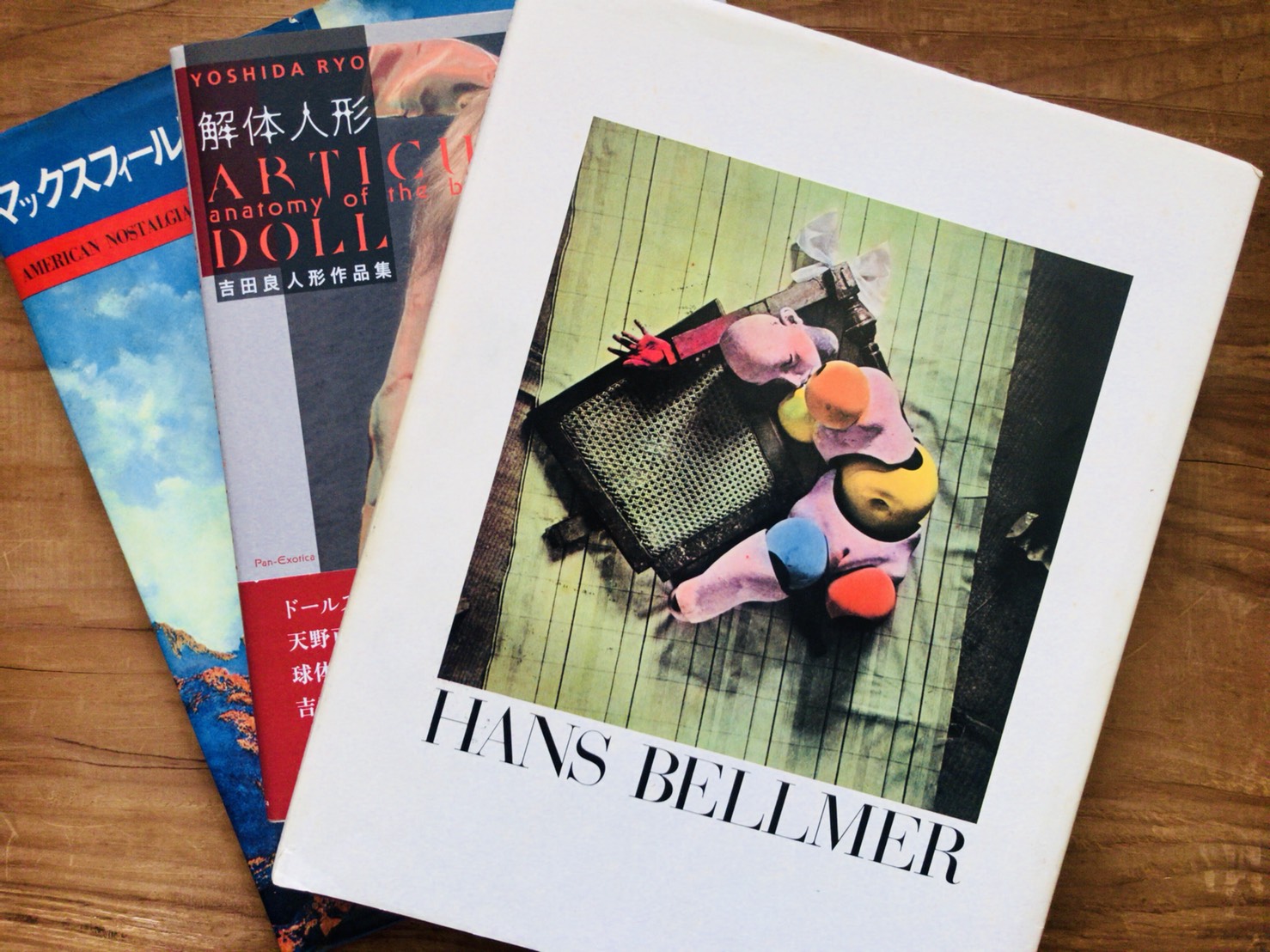




コメントを残す